地球上では、1日は24時間とされている。これは、太陽が前日と同じ空の場所に戻ってくるまでの時間だ。地球の唯一の衛星である月は、約27日かけて地球の周りを1周し、平均距離384,399km(~238,854.5mi)の軌道を回っている。太古の昔から、人類は太陽と月、そしてそれらの恒星期と朔望期を記録してきた。地球と月がどのような軌道を描いているかは、私たちの知る限りずっと同じであり、私たちはそれを当たり前のこととして受け止めてきた。
しかし、かつて月が地球に大きく近づき、1日の平均時間が現在よりずっと短かった時代があったという。中国とドイツの研究者が行った最新の研究によると、25億年前から5億4100万年前まで続いた先カンブリア時代の地質時代である原生代の10億年間は、1日の平均時間が約19時間であったことが分かったのだ。このことから、地球上の1日の長さは、従来考えられていたように徐々に長くなるのではなく、長い間一定であったことが分かる。
この研究は、中国科学院大学地質・地球物理学研究所および地球惑星科学大学のCAS State Key Laboratory of Lithospheric Evolutionの地質科学教授であるRoss N. Mitchellと、元はドイツのチュービンゲン大学で、現在はオーストラリアのカーティン大学The Institute for Geoscience Researchで研究員を務めるUwe Kirscherにより行われた。彼らの研究の詳細を記した「Mid-Proterozoic day length stalled by tidal resonance」と題された論文は、最近『Nature Geosciences』に掲載された。
過去数十年間、地質学者は、干潟から採取された層が保存されている特殊な堆積岩を調査した。潮の満ち引きによってできた堆積層の数を数えれば、過去の地質時代の1日の活動時間を知ることができるのだ。しかし、そのような記録は稀であり、調査されたものは年代について論争になることが多かった。しかし、1日の長さを推定する方法として、MitchellとKirscherが研究に用いた「サイクロストラティグラフ法」というものがある。
これは、地球の軌道の偏心・斜角の変化が気候に与える影響を表す「ミランコビッチ・サイクル」を、堆積物のリズミカルな積み重ねから検出する地質学的手法だ。近年、古代を対象としたミランコビッチの記録が急増している。実は、この7年間だけで、地質学上の古代に関するデータの半分以上が得られているだ。これにより、MitchellとKirscherは、それまで証明されていなかった理論を検証することができた。Kirscherが最近のCASのプレスリリースで説明している通りだ:
「歳差運動と斜位という2つのミランコビッチ・サイクルは、空間における地球の自転軸のぐらつきと傾きに関連している。そのため、初期の地球の自転が速いと、過去の歳差運動や赤緯の周期が短く検出されることがある。このため、もし過去にこれら2つの相反する力が互いに等しくなった場合、そのような潮汐共鳴によって地球の昼の長さの変化が止まり、しばらくは一定に保たれたことでしょう」。
つまり、この説は、過去において、日長が徐々に長くなるのではなく、長期間にわたって一定の値を保っていた可能性があるとするものだ。太陽からの荷電粒子(太陽風)の「押し出し」が、日中の大気の加熱に関係する「太陽大気の潮流」がその重要な要因である。これは、月の重力の「引き」によって起こる「月潮」が、海面の上昇や下降に関係しているのと同じだ。しかし、月の重力が地球の自転をゆっくりと遅らせるのに対し、太陽は自転を早める役割を担っていた。
太陽潮汐は、現在では月潮汐ほど強くはないが、昔はそうでなかったかもしれない。過去に地球の自転速度が速かった時代には、月の引力の影響はもっと弱かったはずだ。MitchellとKirscherがデータの集大成を調べたところ、20億年から10億年前の間に、地球の昼の長さは長期的な増加を止め、約19時間で止まっているように見えることがわかった。Mitchellによると、この期間は「10億年」または「退屈な10億年」とも呼ばれる。
この新しい結果で特に興味をそそられるのは、”退屈な10億年”が、大気中の酸素含有量の2つの大きな上昇の間に起こったことだ。それは、光合成細菌が大気中の酸素量を劇的に増加させた「大酸化現象」と、地表全体(またはそれに近い部分)が氷に覆われた氷河期「スノーボールアース」である「氷河期」である。この結果が確認されれば、地球の自転の進化が大気の組成と関係していることを示すことになる。

また、光合成細菌が現代の大気レベルに達するほどの酸素を作り出すには、より長い日数が必要だったという考えも支持された(24%)。しかし、この研究の最大の意義は、過去の地球の自転(「パレオローテーション」)に対する天文学者の認識をどのように変えるかということだ。長い間、月が地球の自転エネルギーを徐々に吸収し、地球を減速させ、月を高い軌道に乗せ、24時間の日を作り出したという説があった。しかし、今回の結果は、20億年前から10億年前の間に、そのプロセスに中断があったことを示すものである。Kirscherは次のように要約している:
「地球の自転モデルの多くは、過去にさかのぼると、昼の長さが一貫して短くなることを予測している。ミランコビッチの2つの周期、歳差運動と斜位運動は、地球の自転軸が宇宙空間でぐらついたり傾いたりすることに関係しています。したがって、初期の地球の自転が速かったことは、過去の歳差運動や赤道儀の周期が短かったことで検出できます」。
この記事は、MATT WILLIAMS氏によって執筆され、Universe Todayに掲載されたものを、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)に則り、翻訳・転載したものです。元記事はこちらからお読み頂けます。





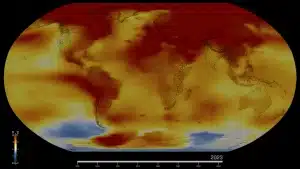

コメントを残す